公開日:2025/10/08
更新日:2026/01/23
- 乳酸菌
古くて新しいプロバイオティクス "ラクリス" ー科学は記憶を継いでいくー
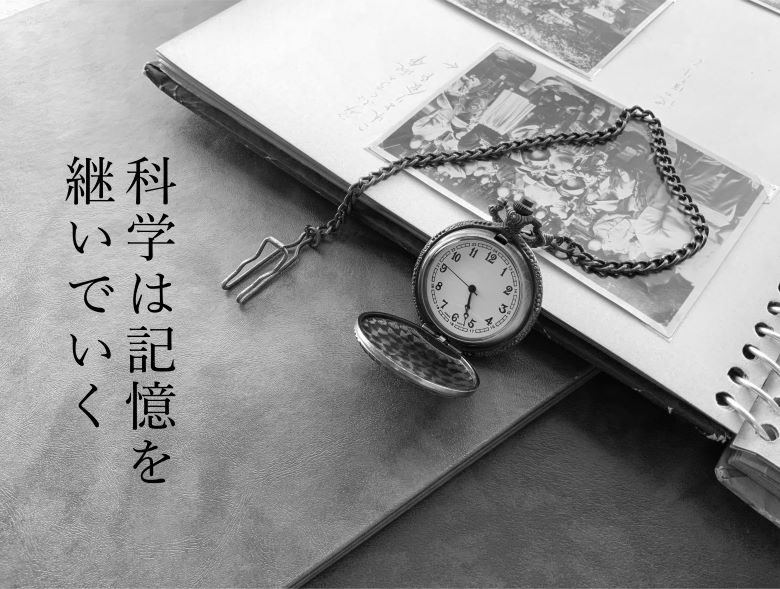
長い年月、絶え間なく歩みを続けた菌があった。
その歩みを支え、信じ続けた者たちがいる。
人知れず、その菌は静かに役割を果たしてきた。
私たちの生活の中にひっそりと息づきながら。
その菌は受け継がれ、日本の技術とともに歩んできた。
そして今、次の未来へと受け継ごうとしている。
これは、その菌が辿ってきた物語である。
◆ 戦中の乳酸菌コレクションの喪失
第二次世界大戦中、日本国内の研究機関では、電力や人手の不足によって、乳酸菌株の保存や維持が難しくなっていた。
その結果、多くの乳酸菌コレクションが失われ、機能の研究用にも大きな影響を及ぼすことになった。
◆ 新たな乳酸菌の発見
1947年、東京大学農学部の坂口謹一郎教授(発酵学の権威)は、中山大樹博士(後の山梨大学名誉教授)に、乳酸菌 Lactobacillus delbrueckii の分離を依頼した。
中山博士が厳しい環境下で菌株を採取し、教授に見せたところ、「これはデルブリュッキーではないね。捨てる前に、まぁ一度煮てごらん」と助言を受けた。
加熱処理されたその菌は、翌日に再び発育し、胞子を形成する乳酸菌であることが判明した。
この偶然の発見が、有胞子性乳酸菌の存在を明らかにすることになった。
◆ 緑麦芽からの菌株分離
1949年、中山博士は日本麦酒工場の緑麦芽から、耐熱性で胞子を形成し、乳酸をより多量に生産する菌株を分離した。
この菌株は現在 Bacillus coagulans(Weizmannia coagulans) と同定され、食品や医薬品への応用が進められている。
◆ 臨床試験と製品化
中山博士と三共株式会社(現・第一三共)の研究チームは、菌株の培養条件や胞子形成条件を明らかにし、さらに人体への安全性や整腸効果についても臨床試験を重ねた。
その結果、整腸効果や食品としての使用が認められた。
◆ 有胞子性乳酸菌の特徴と分類
有胞子性乳酸菌は、胞子を形成することで熱や酸に強く、腸まで生きて届くという特性を持っている。
一般的な胞子形成乳酸菌には Bacillus coagulans、Sporolactobacillus inulinus などがあるが、産業用途としては Bacillus coagulans が主に用いられている。
日本の医薬品規格(局外規)にも「有胞子性乳酸菌」として収載されており、その存在は今の発酵・微生物研究の基盤を形づくっている。
有胞子性乳酸菌の発見と応用は、日本の発酵学と微生物学の歩みにおいて、大きな意味を持っていた。
とりわけ、坂口謹一郎教授と中山大樹博士の協力がなければ、現在のプロバイオティクス製品の礎は築かれていなかったかもしれない。
いま私たちは、その礎の上に立っている。
それは、見えない菌が技術とともに折り重なった、
目には見えない地層のような礎なのだ。
折り重なる歴史を引き継ぐ私たちは、
始まりを知っている。そして今、
その礎とともにこの菌を未来へ繋ごうとしている。

ラクリスの開発経緯
1949年
山梨大学 中山博士が緑麦芽から有胞子性乳酸菌を分離
1961年
三共㈱にてコレステリン分解菌のスクリーニングの一つとして採用
その後ビオフェルミン(ビオフェルミン株)の対抗品として開発開始
1964年
三共㈱より、有胞子性乳酸菌を含む医薬品としてラクボン発売
1966年
三共㈱より、食品用ラクリス-S(50億個/g)発売
飼料用ラクリス-10(10億個/g)発売
2000年
ラクリス-S顆粒を発売
2007年
ラクリスの事業を三菱化学フーズ㈱が取得
2016年
ラクリス発売50周年
2019年
食品用ラクリス-15(150億個/g)発売
